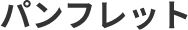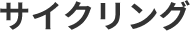春日神社

宝亀年間に坂上田村麿が三笠山の春日大社(奈良県)の神を勧請したのが起源と伝えられる古社。天授2年(1376)に坂上正研澄が社殿を建立しましたが、応永の乱(1399)の時兵火にかかりました。 その後、豊臣秀吉の根来寺攻めの時に再び焼失し、後に地元の人々により再建され佐野の総社となりました。明治5年村社となり、明治41年~42年(1908~1909)の神社合祀の際には、佐野町域にあった大小29の神社がここに合祀されました。 境内地内には、江戸時代の豪商食野家・唐金家が寄進した燈籠があります。
本殿は隅木(すみき)入一間社春日造、軒唐破風(のきからはふ)であり、江戸時代中期のものと考えられています。7月23、24日が夏祭りで、3基の太鼓台が勇壮に街を練り回るふとん太鼓が行われています。(現在は、熱中症対策として猛暑、残暑を避けた日程で実施されています。詳しく日程は、ふとん太鼓のページにて確認してください。)
住所 : 大阪府泉佐野市春日町4-12
電話番号 : 072-464-0235
画像ギャラリー

地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
泉佐野市観光協会
072-469-3131